社用車で事故を起こしてしまった場合、従業員と会社で責任の内容が異なります。ここでは、従業員と会社それぞれの責任の内容について紹介します。
【ケース別】社用車で事故を起こした時の対処法・従業員と会社の責任範囲

社用車を利用する企業やその従業員にとって、業務中の事故は決して他人事ではありません。万が一社用車で事故が起きた場合、従業員だけでなく会社側も責任を問われる可能性があります。しかし、従業員と会社がどのような責任を負うのか、具体的に理解している方は多くないかもしれません。
本記事では、社用車で事故が発生した際の対処方法や、従業員と会社が負う責任についてケース別で紹介します。万が一の事態に備え、従業員側・会社側のどちらの観点からも、必要な対応や対策の参考にしてください。
目次
社用車での事故、従業員と会社が負う責任範囲の違いとは?

社用車を運転していた従業員が負う責任
運転していた従業員は、民法709条に基づいて、民事上の損害賠償責任を負うことになります。例えば、事故によって相手のクルマを損傷させたり、相手に怪我を負わせた場合には、クルマの修理代や治療費などの賠償義務が発生します。
実際に支払う金額については、過失割合や加入している保険の適用範囲、相手の損害の程度などで異なります。また、詳しくは後述しますが、民法715条に基づき会社が賠償責任を負うケースもあります。
社用車を管理している会社が負う責任
社用車を管理している会社は「使用者責任」を負う可能性があります。
使用者責任とは、従業員が業務中に起こしたミスによって第三者に損害を与えた際に、直接的な加害者ではない雇用主や管理者側が負う責任のことです。
従業員が業務中に社用車で事故を起こした場合「会社の指揮命令のもと、業務中に運転を行い、事故を起こした」ことが認められれば、会社に使用者責任が生じる可能性があります。
ただし、すべての場合に使用者責任が発生するとは限りません。従業員が会社の指示に反して私的に社用車を使用して事故を起こした場合など、状況によって責任の有無が変わるケースもあります。具体的な責任の有無は、判例や個別の状況によって異なるため注意が必要です。
また、自動車損害賠償保障法に基づき「運行供用者責任」を負う場面もあります。この法律は、社用車を管理・提供している会社が、事故の被害者に対して十分な補償を提供できるよう、損害賠償責任を広く認めるものです。
例えば、従業員が重大な物損事故や死亡事故を起こし、賠償額が数千万円規模になる場合でも、被害者が適切な補償を受けられる仕組みになっています。
この法律は、業務の外部委託や下請け業者が関与している場合でも適用されることがあります。
そのため、会社としては従業員の運転能力を適切に把握し、運転中のルールや管理体制を徹底することが求められます。日頃から安全運転の教育や研修を行い、リスクを未然に防ぐ取り組みが不可欠です。
事故のケース別に見る会社が負う責任範囲

社用車で事故が発生した場合、その状況によって会社が負う責任の範囲は異なります。特に「業務中に起きた事故」と「業務時間外に起きた事故」では、会社の責任の内容や程度が変わります。ここでは、事故のケース別に会社の責任範囲について説明します。
業務中に起きた社用車での事故
業務中に発生した事故の場合、会社は「使用者責任」と「運行供用者責任」の両方を負うことが一般的です。従業員が会社の指揮命令のもと業務を遂行している最中に事故を起こした場合、会社には従業員の行為に対する法的責任が求められることになります。
ただし、具体的な責任範囲は、事故の詳細や会社と従業員間の契約内容、社用車の利用規定等によって異なる場合があります。
業務時間外に起きた社用車での事故
業務時間外であっても、会社が従業員に社用車の利用を許可している場合には、「運行供用者責任」が発生することがあります。これは、会社が車両の管理者としての責任を問われるためです。
また、従業員が無断で私的利用をしていた場合でも、会社と従業員の関係や、個々の状況によって、会社が責任を問われる場合もあるようです。
このようなリスクを避けるためにも、会社は社用車の使用ルールを明確に定め、従業員に周知することが重要であると言えるでしょう。
参考:一般社団法人 日本自動車連盟 (JAF) [Q]社員が社用車を私用で運転中に起きた事故。会社の責任は?
社用車での事故発生時に取るべき対応

社用車で事故が発生した際は、速やかに適切な対応を取ることが重要です。対応が遅れると、事故の被害が拡大するだけでなく、被害者とのトラブルに発展する可能性もあります。ここでは、社用車での事故発生時に取るべき対応について解説します。
従業員が事故発生時に行うべき対応
まずは、負傷者の救護が優先です。すぐに救急車を呼び、近くの医療機関へ運ぶなどの手配を行いましょう。もし救護の措置をとらずに現場から立ち去ってしまうと、運転者はひき逃げ(救護義務違反)となってしまいます。
そして、交通事故を連鎖させないために、クルマを安全な場所に移動します。状況に応じて発炎筒を点火し、停止表示機材を設置して、二次被害を防ぎます。
安全が確保されたら、速やかに警察に連絡します。警察へ報告する際には、事故の発生日時と場所、負傷者の有無など状況を伝えます。
また、現場の状況や相手の連絡先、相手のナンバープレートの番号などを記録することも重要です。これらの情報は、保険会社や会社に報告する際に必要となります。
従業員は、事故発生時の動揺によって適切な対応が取れない場合があります。そのため、会社としては、事前に事故対応手順を周知し、シミュレーションを通じて従業員が冷静に行動できるよう備えておくことが重要です。
従業員から事故の連絡を受けた会社が行うべき対応
従業員から事故の連絡を受けた際には、速やかに保険会社へ連絡を入れましょう。事故発生から保険会社への報告が遅れると、補償の手続きにも遅れが生じる可能性があるため、迅速な対応が求められます。
従業員から提供された事故の詳細情報(負傷者の有無、相手の連絡先や車種など)を基に、必要な補償の手続きを進めます。被害者への対応が遅れると、トラブルが長引く可能性があるため、早めに対応することが望ましいです。
また、事故を起こした車両がリース車両の場合には、リース会社にも忘れずに連絡を入れましょう。リース会社との契約内容によっては、修理や代替車両の手配が必要になる場合もあります。
従業員の事故を防止するためには

社用車の利用において、事故を未然に防ぐためには、会社として従業員への対策を事前に講じることが欠かせません。特に、一定の規模以上の車両を保有する事業者には法令に基づく責任が課されますが、小規模事業者でも参考にできる方法は多くあります。ここでは、規模を問わず役立つ具体的な取り組みを紹介します。
一定規模以上の車両を保有する事業者の取り組み
一定規模以上(白ナンバー車両5台以上、または貨物運送事業の場合)の車両を保有する事業者には、法律に基づき「安全運転管理者」や「運行管理者」を選任する義務があります。
安全運転管理者
安全運転管理者は、従業員が安全運転を行えるように指導を行い、車両の点検や交通事故防止のための施策を推進する役割を担います。さらに、選任後は15日以内に都道府県公安委員会に届け出ることが義務付けられています。
参考:警察庁 安全運転管理者の業務の拡充等
運行管理者
貨物運送事業者の場合は、運行管理者を選任する必要があります。運行管理者は、運行計画の作成や運転者の健康状態の確認、不適切な運行スケジュールの防止を行い、安全で効率的な運行を確保します。
参考:国土交通省 運行管理者について
小規模事業者でも取り入れられる方法
小規模事業者においても、法令で義務付けられていない部分での自主的な取り組みが重要です。例えば、以下のような方法は規模に関わらず、事故の防止に役立てることができるでしょう。
安全運転講習会を定期的に開催する
安全運転講習会は、従業員に交通ルールや基本的な運転マナーを再確認させるための有効な手段です。特に、長年運転をしている従業員ほど、基本的なルールを見落としている可能性があります。「これくらい知っているだろう」と考えず、道路交通法や運転の基礎を定期的に振り返る機会を提供しましょう。
また、道路交通法は頻繁に改正されています。改正内容について講習会で説明をすると、事故の防止に繋がるのはもちろん、交通違反の抑制にもなるでしょう。
従業員の運転技術を把握する
従業員一人ひとりの運転技術を把握することは、事故リスクを軽減するうえで重要です。ドライブレコーダーや運転シミュレーターを活用し、従業員の運転時の癖や改善点を確認する仕組みを導入しましょう。
安全運転意識を啓蒙する
従業員が日常的に安全運転を意識できるよう、事故の事例や具体的な損害の例を定期的に共有することも効果的です。たとえば、「事故を起こした場合、どのような責任を負うのか」「会社全体にどのような影響が及ぶのか」といった実例を紹介することで、安全運転への意識が高まります。
事故を日頃から防ぐには、日産フィナンシャルサービスの法人カーリース「リスクマネジメントサービス」が便利!
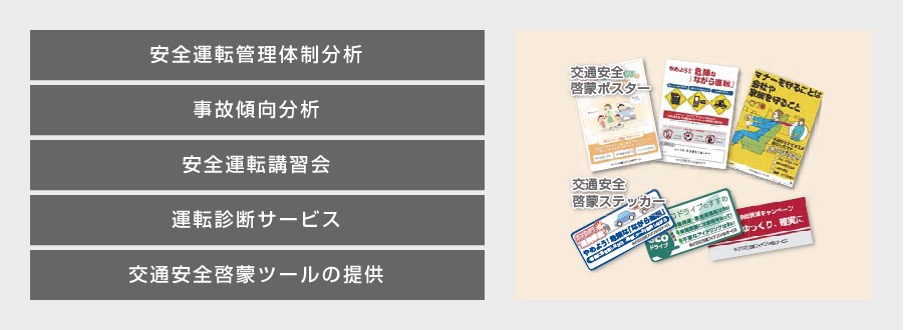
日産フィナンシャルサービスでは、社用車の事故防止活動を支援する「リスクマネジメントサービス」をご用意しています。お客さまのご要望や状況に合わせて、サービスをカスタマイズすることができます。
ここでは、「リスクマネジメントサービス」の6つのメニューを紹介します。日産フィナンシャルサービスの法人カーリースをご契約いただいているお客さまのみご利用いただけるメニューもありますので、詳しくはお問い合わせください。
安全運転管理体制分析
簡単なアンケートをもとに、車両管理体制の取り組み状態を診断いたします。「全社対策」「管理者対策」「運転者対策」の切り口で、現状を分析したレポートを作成するため、問題があった場合に会社内で適切な対策を講じやすいのが特徴です。
事故傾向分析
事故統計によりパターン化された多発事故形態や、お客さまが今まで起こしてきた事故の問題点などを解析した上で、事故防止活動に向けた最適なプランを策定します。どのような事故が起こりやすいのか傾向を把握することで、効果的な事故防止活動のサポートになります。
安全運転講習会
従業員の方を対象に、安全運転講習会を有償で実施します。運行管理者向け、一般社員向けなどカスタマイズも可能です。実施にあたっては、お客さまの現状(事故発生状況等)を踏まえ、多発事故・重大事故の事例紹介とその防止策、事故が及ぼす影響等について弊社専門講師が解説いたします。
安全運転意識啓蒙ツール
交通安全に対する有益な情報をタイムリーに提供する「ニュース配信」や、運転者に事故への意識を高めてもらうための「交通安全ポスター」、「安全運転啓蒙ステッカー」を提供します。運転者に注意喚起や気づきを与えることで、事故を未然に防止します。
運転診断サービス
ドライブレコーダーを社用車に設置し、映像の分析を有償で行います。管理者から従業員に対して運転指導をする際に役立つのはもちろん、従業員自身が運転を見つめ直す際にも活用できます。
教習所紹介
事故多発者、新入社員、ペーパードライバー等への再教育として、提携教習所を紹介し、個別指導を有償で行います。
また冬季には降雪地での運転に不慣れな方向けに雪道体験講習会を実施しております。
まとめ:社用車で事故を起こさないために常日頃から意識することが大事
社用車で事故を防ぐには、従業員の安全運転意識を高めるとともに、会社が適切な管理体制を整えることが重要です。日々の安全運転教育やルールの明確化、運転データを活用した改善指導を行い、事故を未然に防ぐ環境を整えましょう。
それでも事故を完全に防ぐことは難しいため、万が一の際に適切に対応できるよう、対応手順を事前に明確化し、従業員に周知しておくことが必要です。
事業者の規模に応じた取り組みを実践し、従業員が安心して働ける安全な運行環境を作り上げることが大切です。
法人や個人事業主がクルマを導入するなら、日産フィナンシャルサービスの法人カーリースがおすすめ!
日産フィナンシャルサービスの法人カーリースなら、導入にかかる手間や費用を抑えられるのはもちろん、車両購入手続きから税金納付、保険加入、整備手配など面倒な事務処理を日産フィナンシャルサービスが代わって行いますので、管理の手間を大幅に削減することが可能です。
また、オンラインで見積もりが可能で、Webから審査申込みもでき、契約手続きも来店不要であるため、ディーラーへ何度も来店せずとも納車まで進めることができます。
リスクマネジメントサービスを活用すれば、事故の防止にも繋げられます。社員の事故に対する意識を高めるためのサービスも数多く利用できるため、会社全体の安全意識の向上も見込めます。
ぜひ日産フィナンシャルサービスの法人カーリースをご検討ください。




